「犬山市市民活動の支援に関する条例」制定のプロセス ステップ 1
ページ番号1000749 更新日 令和2年4月1日 印刷
平成11年度は、「各種補助団体等アンケート調査」「市民活動グループへのインタビュー調査」を実施しました。そして、市民活動の支援に関するしくみを市民と専門家がいっしょに考える「市民活動支援研究会」を開催しました。
「市民活動支援に関する研究会」を開催
平成11年7月から月1回「完全公開制」で計7回
| 回数 | 内容 |
|---|---|
| 第1回 | 「おはなし(ミニ講座)(1)」 |
| 第2回 | 「市民活動レポート(1)」「おはなし(ミニ講座)(2)・(3)」 |
| 第3回 | 「市民活動レポート(2)」「おはなし(ミニ講座)(4)・(5)」 |
| 第4回 | 「市民活動レポート(3)」「おはなし(ミニ講座)(6)」 |
| 第5回 | 「市民活動レポート(4)」「ワークショップ(1) こんな活動できたらいいな」 |
| 第6回 | 「ワークショップ(2) あったらいいな。こんなしくみ」 |
| 第7回 | 「ワークショップ(3) 描いて ましょう。支援のしくみ」 |
| 番外編 |
「シンポジウム 市民ネットワークをつくろう!」 市民活動発表会ほか |
- 研究会前半は、専門家によるミニ講座「おはなし」や、犬山市で実際に活動されているグループからの「市民活動レポート」などの意見交換を行いました。
後半は、市民と専門家が参加するワークショップ形式で、犬山型の市民活動支援のしくみについて具体的に話し合い、研究会からの提案としてまとめました。
研究会メンバー(敬称略・平成11年当時)
有賀 隆(名古屋大学大学院工学研究科助教授)
鈴木 誠(岐阜経済大学教授)
梅田 寛(犬山市立図書館長・前犬山市助役)
高田 弘子(都市調査室代表)
荻田 誠一(名古屋経済大学経済学部教授)
昇 秀樹(名城大学情報都市学部教授)
木野 秀明(市民活動グループ)
安田 文吉(南山大学文学部教授)
川島 紀之(市民フォーラム21・特定非営利活動法人センター理事)
米澤 邦弘(犬山市観光協会副会長)
研究会からの提案
「全体の拠点」「地域ごとの拠点」「共通の支援メニュー」が3つのポイントです。
1.全体支援型拠点(センター)
市民活動ネットワークの拠点。各地域での取り組みをつなげたり、個人からグループまで自由に集まり、気軽に情報交換や印刷・製本などができる部室感覚のセンターオブセンター。
2.地域支援型拠点
地域の学校、公民館などの既存公共施設から、空き家にいたるまで既存の地域資源を活かした拠点スペース。地縁組織からテーマ活動団体までいっしょに活動できるように。
3.共通支援プログラム(資金・情報等)
- 「まちづくり市民バンク」:透明性のあるファンド(基金)を設立。分野別に基金収集。
- 「提案公募型の助成システム」:グループから活動提案発表を募り、公開審査により助成。
- 「いぬやまマネー(犬山型地域通貨)」:犬山型の地域通貨(エコマネー)のアイディア。
- この他にも「メーリングリスト こんな活動やってます」の作成や「シンポジウム 市民活動発表会」「駅前チャレンジショップ」の活用など、市民活動グループのネットワークをつくる具体的なプロジェクトが、すでに実現しています
研究会の風景
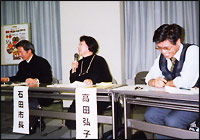

このページに関するお問い合わせ
市民部 地域協働課 地域担当
電話:0568-44-0349 犬山市役所 本庁舎3階

